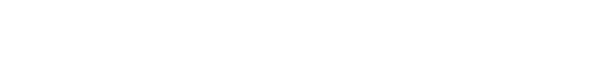『バッハと東京塩麹 “Flow of Time”に寄せて』文:額田大志
2025/09/10
9月14日(日)に開催する東京塩麹の6年ぶりの単独公演『Flow of Time “Recomposed : Bach’s Invention”』
今週末の開催に先駆けて、今作の作曲者である額田大志の寄稿文を公開いたします。
ぜひライブを観る前に、ご一読ください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
バッハと東京塩麹 “Flow of Time”に寄せて
*音楽が持つ「時間の流れ」
9月14日(日)に開催する東京塩麹の6年ぶりの単独公演『Flow of Time “Recomposed : Bach’s Invention”』が、今週末に迫って来ました。『Flow of Time』は日本語に訳すると「時間の流れ」となります。もう少し噛み砕くと、1つの音楽の中には、2つ以上の「時間の流れ」が存在することを、その場に居合わせたお客さんと共有したい、そんな気持ちが企画段階から強くあります。
音楽、特にライブでは、歌詞や曲調といった一つのまとまったイメージを共有することが重要視されることも多いですが、東京塩麹の音楽は様々な楽器の集合体だったりと、複層的な構造を持っています。そうした構造的な楽しみ方をするには、ある程度音楽への熟練度が必要な面があり、それはそれで良いのですが、一方で東京塩麹の音楽は構造の妙(リズムの重なりや、反復、音と音のズレ)そのものを、一つの聴きどころとして追求している側面があります。なので、楽曲のそんな魅力を今まで以上にライブで共有したい……という思いが募り、今回は映像演出を多分に取り入れ、複数のリズムや楽器のフレーズ、それぞれを注視しながら全体の楽曲を聴く、といった新鮮な体験を作るべく、最後の準備に奔走中です。
書き下ろした1時間ほどの楽曲は、これまで以上にいくつかの「時間の流れ」、音楽用語としては楽曲のリズム、速度、ズレなどが、同居したものになりました。ただあくまでも、音楽然として聴いてもらうというのも、今回の題材として取り上げたバッハと繋がる部分であり、言葉を変えると、身体が揺れ動く、音楽として躍動感がある、そんなダイナミズムと構造的な面白さ、それらを両立するようなライブです。
*バッハ『インヴェンション』のリコンポーズ
バッハは東京塩麹が特に結成時に追求していたミニマルミュージック(短いフレーズの反復や重なりによる音楽)の、ある種の始祖的な人と考えており、かつ、音楽的な思考も東京塩麹と類似する部分もあり、今回、思い切って取り上げるに至りました。
バッハの代表作の一つである『インヴェンション』は、今でこそピアノの練習曲として有名ですが、元々は演奏者の作曲と演奏技術の習得を目指して書かれた楽曲です。当時は、今よりも演奏者と作曲者の垣根がなく、バッハ自身もオルガン奏者として有名だったり、楽曲も自由度の高い即興的な演奏が求められていました。なお、そうした演奏者の即興性を踏まえたパートも、今回のリコンポーズ版では登場予定です。
『インヴェンション』はそれぞれの声部(ピアノだと右手と左手)が独立した動きをしており、一つの音楽ではあるけれど、それぞれの声部が、それぞれの動き方をしています。わかりやすく言い換えると、右手と左手のフレーズがものすごく緻密に設計されているのに、音楽的にイキイキとしているというのも特徴です。今回はこうした、独立した旋律が絡み合うことも、複数の「時間の流れ」と捉えています。
ただし、それは『インヴェンション』を練習、習得しないと、音楽の構造的な美しさがわからない……という裏返しでもあるかと思います。当時はそもそもライブ/コンサート文化がほぼ存在しなかったため、演奏者と作曲家、観客がある程度同列に存在できたかもしれません。しかし、現代的に解釈をするという点では、文化的に成熟している音楽のライブ/コンサート文化を避けることは難しく、やはりそうした機会を通じて、構造の面白さを伝える、『インヴェンション』を弾いてはいない人たちと共有する、というも重きを置いています。『インヴェンション』という楽曲を通じて、バッハが達成したかった音楽の習得を、リコンポーズと映像演出によって、実際に弾いてはいないお客さんにも届けたい……というのは、バッハが作曲した背景としても、繋がりがあるように思っています。
一方、ここまでお読みいただいた方は、ライブだけど、なんだか難しそう……と思った方も、正直多いと思います。ですが、バッハをはじめたクラシック音楽の楽曲を浮かべてみると、非常に聴き心地がよいように、『インヴェンション』もとても耳馴染みのよう音楽であり、それ自体も非常に大事な要素かと思っています。コンセプト中心の作曲に陥るのではなく、音楽として誰もが疑わないレベルの形式を持った上で、構造的な美学に踏み込んでいく、そんなことでしょうか。個人的には、建築のようなものだと思っています。どれだけ風変わりな住居でも、必ず入り口があったり、人が住めるようになっているといった機能性は必ずある、そんな、音楽としての疑いのなさの上で、注視するとより面白い、そんなことをリコンポーズ版でもできるように作曲を進めてきました。
また最後に、東京塩麹とバッハの関連をもう一つ挙げておきたいと思います。バッハの楽曲は、例えばベートーヴェンの交響曲第9番(歓喜の歌)のように明確な対象、作家の主張が意図されたものは少なく、音楽のための音楽であったり、神や自然といったより広い事象を想起させることがあります。東京塩麹の音楽に対する向き合い方も、音楽が持つ音の重なりの美しさや、繰り返しによる効果といった、部分に特化している傾向があり、そうした音楽への向き合い方にも共感する部分がありました。これは、決して音楽はノーメッセージなのが良いと言っているわけではなく、音楽それ自体が持っている響きや重なりを、楽曲の良さとして追求するということも、音楽を通して何かを伝えるという意味で、特定の対象や主張を込めた音楽と同じくらい重要な営みだと考えています。
と、以上のような準備を踏まえて、東京塩麹、そして多くのスタッフが一日限りのライブに向かって準備を進めています。バッハと東京塩麹が300年の時を経て邂逅する瞬間をお見逃しなく!
東京塩麹
額田大志
_
東京塩麹 単独公演『Flow of Time “Recomposed : Bach’s Invention”』
2025年9月14日 (日)
14:00 / 17:30 全2公演
会場:ゲーテ・インスティトゥート東京 ホール
チケット予約・詳細
https://tokyoshiokouji-2025.peatix.com
<出演>
東京塩麹
トランペット:渡辺南友
キーボード:中山慧介
シンセサイザー:額田大志
ギター:テラ
ベース:初見元基
ドラム:渡健人
パーカッション:高良真剣
※トロンボーンの渡邉菜月を除く7名のメンバーが出演します。
<スタッフ>
作曲:ヨハン・ゼバスティアン・バッハ、額田大志
空間構成:山口 涼(蜃気楼)
映像ディレクション・宣伝美術:高良真剣
撮影・映像システム:ニュービデオシステム
舞台監督: 守山真利恵、森部璃音
音響:山川権(WEAVE-ON Sounds LLC.)
照明:平曜
衣装:鈴木啓佑
制作:柴田聡子
協力:ゲーテ・インスティトゥート東京
助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 【東京ライブ・ステージ応援助成】
企画・製作・主催:東京塩麹
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■